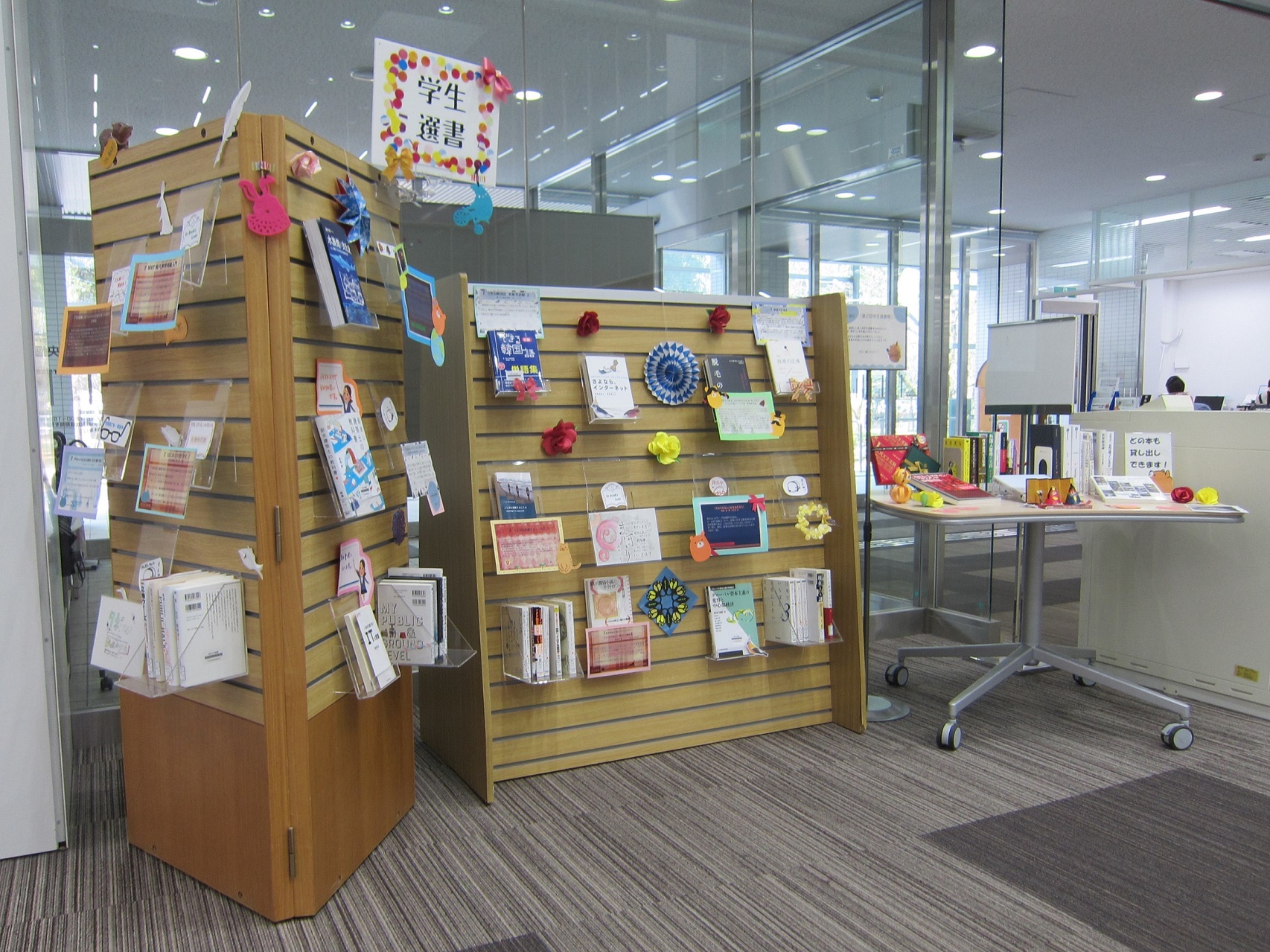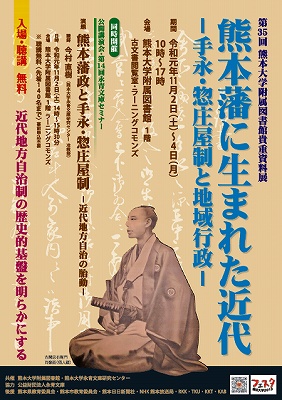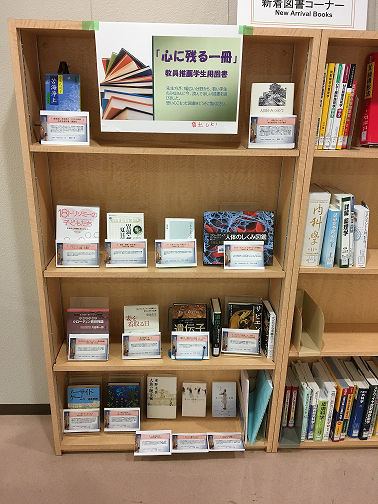「科学道100冊」
期間:令和2年3月6日(金)~4月中旬
場所:附属図書館中央館1Fロビー
今回のロビー展示は、
理化学研究所(理研)と編集工学研究所による組織「科学道100冊委員会」が実施している、
「科学道100冊プロジェクト」にて作成された選書リスト「科学道100冊 2019」をもとに開催します。
「科学道100冊プロジェクト」とは、
『"書籍を通じて科学者の生き方・考え方、科学のおもしろさ・素晴らしさを届ける"事業』です。
「科学道100冊 2019」は、旬のトピックなど3つの軸で選んだ「テーマ本」50タイトルと、
時代をこえる良書として選んだ「科学道クラシックス」50タイトルの合計100タイトルで構成されています。
2019年の3つのテーマは「元素ハンター」「美しき数学」「科学する女性」です。
---
「科学道100冊」について詳しくはこちらから↓
今回のロビー展示では、
「科学道100冊 2019」書籍リストにある、100タイトルのうち、
中央館に所蔵のある、74タイトル(80冊)を展示しています。
【展示図書リストは こちら から!】(請求記号順に並んでいます)
ぜひご覧ください!
☆展示されている本はすべて借りることができます!